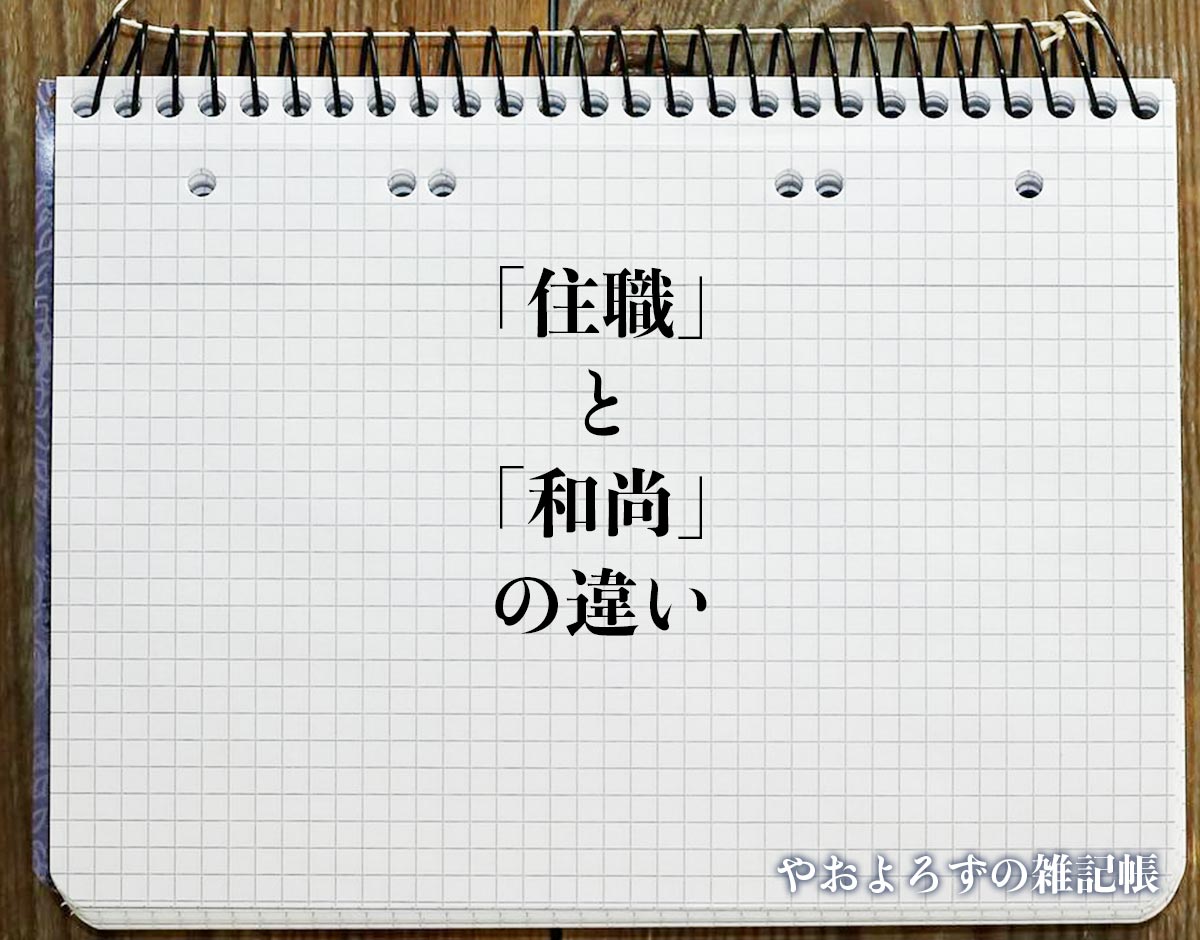この記事では、「住職」と「和尚」の違いを分かりやすく説明していきます。
「住職」とは?
「住職」とは、「じゅうしょく」と読みます。
「住職」は、お寺におけるお坊さんの役職を表す言葉で、そのお寺に住み込みで働くお坊さんの中で代表者に対して使用する言葉です。
複数のお坊さんが住み込みで働くお寺では、基本的に「住職」は一人です。
「住職」を補佐しているお坊さんは「副住職」と呼ばれ、「住職」が女性の場合は「庵主」、「住職」の息子に対しては「若院」という呼び方をします。
お葬式に来ていただいたすべてのお坊さんに対して「住職様」と呼ぶのは間違っていて、そのお寺の代表者にだけ使用できる呼び方でのため、来て頂いたお坊さんがどのような立場の方か確認して呼ぶ必要があると言えます。
「和尚」とは?
「和尚」は、一般的には「おしょう」と読みますが、実は宗派によって読み方が変わります。
真言宗は「わじょう」天台宗では「かしょう」と読みます。
このように宗派によって呼び方が変わるため、宗派を確認する事なく間違った呼び方をしてしまうと失礼にあたります。
「和尚」とは、修行をして一人前となり、自らが戒律を授ける立場となった地位の高いお坊さんを指す言葉であり、前述した「住職」になる資格を得ているお坊さんになります。
「和尚」の語源は古代インドの言葉「ウパージャーヤー」という師匠や先生を意味する言葉が変化したと考えられています。
「和尚」は高い地位のお坊さんに対して使用されるため、お坊さんが一人のお寺の場合「和尚」が「住職」と同様の意味を持っている場合も少なくありません。
規模の大きいお寺になると複数のお坊さんが在職している場合があり、修行中の方などが含まれることもあるので、すべてのお坊さんを「和尚さん」と呼ぶのは間違っています。
また、浄土真宗には戒律という考え方がないため、「和尚」という概念は存在しません。
このため、浄土真宗の場合には「和尚」という言葉は使用できない事を覚えておく必要があります。
「住職」と「和尚」の違い
「住職」と「和尚」の違いは、そのお寺に住み込みで働いており、お寺の代表者については「住職」と呼び、それ以外の修行を経て一人前となっているお坊さんは「和尚」と呼ぶことになります。
お寺に在職するお坊さんが一人の場合は、「住職」の役割を持つ「和尚」と言う事になるのです。
しかし「和尚」という呼び方については宗派によって異なっているため、呼ぶ前にどの宗派であるか確認する必要があります。
さらに、上述したように浄土真宗では戒律の考え方がないため「和尚」という言葉は使用できず、お寺の人という意味の「院家」や「御院」という呼び方をします。
まとめ
「住職」と「和尚」はどちらもお坊さんを表す言葉ではありますが、「住職」はそのお寺の代表者を表す役職で、「和尚」は一人前となり、戒律を授ける立場となった地位の高いお坊さんを指す場合の言葉となります。
「和尚」という言葉は宗派によって読み方が変わりますので、その点を注意しておく必要があるでしょう。