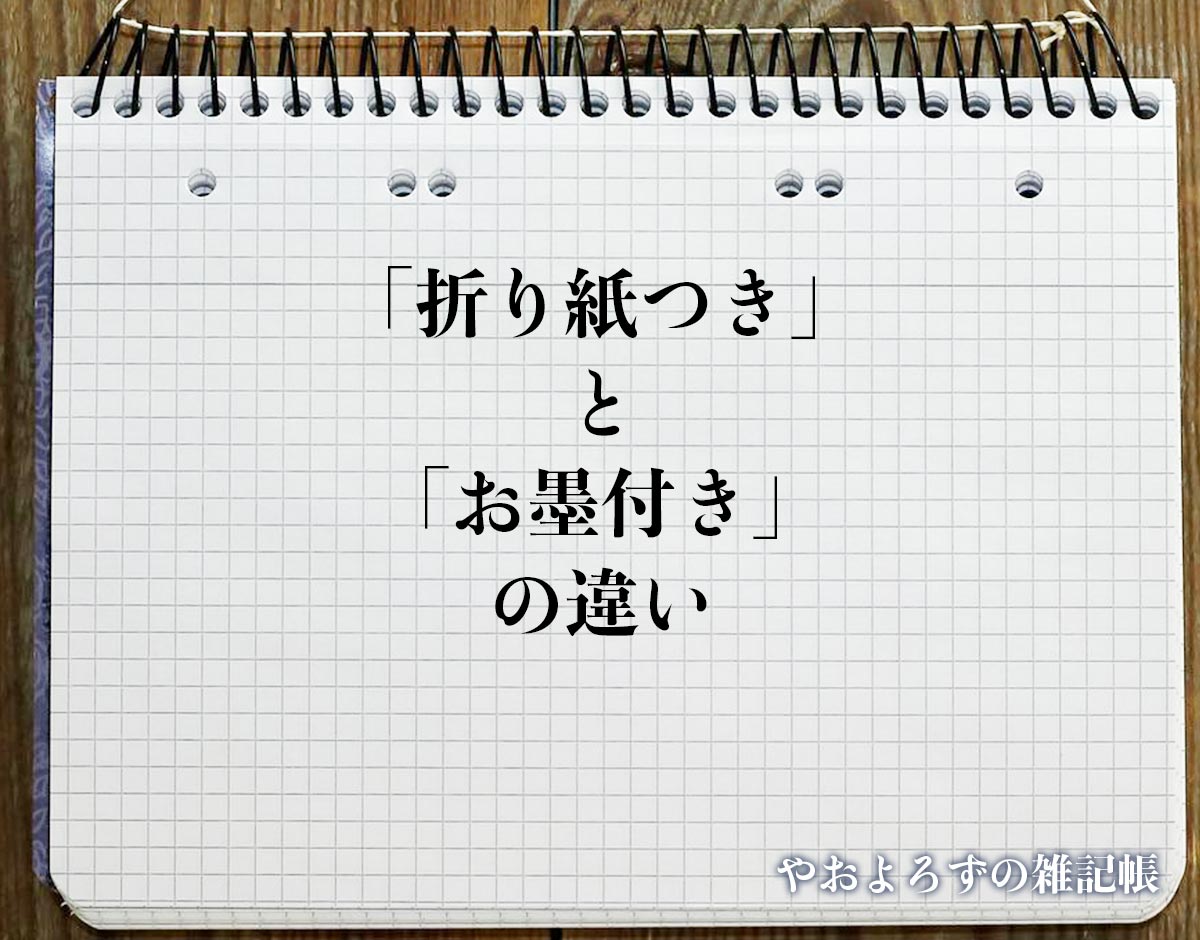この記事では、「折り紙つき」と「お墨付き」の違いを分かりやすく説明していきます。
2つの言葉には、どのような意味と違いがあるでしょうか。
「折り紙つき」とは?
「折り紙つき」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。
「折り紙つき」は「おりがみつき」と読みます。
「折り紙つき」は、「鑑定保証書がついていること。
そのもの」という意味があります。
また「折り紙つき」には、「そのものの価値、資格などに定評のある事。
保証できること」という意味があります。
一般的には、後者の意味で使われることが多くなっています。
例えば、職人の中でも、スキルが高いことに定評がある人は、「この職人の技術は、折り紙つきだ」などと呼ばれることがあります。
また、秘密を打ち明ける相手が、口が堅いことで定評があるという場合は、「口が堅いと折り紙つきのお前にだから、秘密を話すが」などという文章にすることができます。
このように、価値や資格などに定評がある人に対して、「折り紙つき」という言葉を使うことができます。
「お墨付き」とは?
「お墨付き」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。
「お墨付き」は「おすみつき」と読みます。
「お墨付き」は「室町、江戸時代に幕府や大名から、後日の証拠として臣下に与えた花王のある文書」という意味があります。
また「お墨付き」には、「権力や権威のある人の与える保証」という意味があります。
一般的には、後者の意味で使われる言葉になります。
例えば、学生の優秀さを、大学教授が保証するようなとき、「教授がお墨付きを与えた、優秀な学生です」などと表現することができます。
また、その土地の支配者から、店を開いて商売をすることができる保証をもらっている時、「私の店は、○○様からお墨付きをもらっているから、商売できるのだ」などという文章にできます。
他にも、「誰かのお墨付きをもらえなければ、就職ができない」とか、「お墨付きがなければ、国境を超えることができない」などという文章を作ることができます。
「折り紙つき」と「お墨付き」の違い
「折り紙つき」と「お墨付き」の違いを、分かりやすく解説します。
「折り紙つき」には、「そのものの価値、資格などに定評のある事。
保証できること」という意味があります。
一方で、「お墨付き」には、「権力や権威のある人の与える保証」という意味があります。
このように「折り紙つき」は、「価値や資格などに定評があること」を意味するのに対して、「お墨付き」は「権力や権威ある人の保証付き」であることを意味があるという違いがあります。
何かの価値や資格に定評がある場合は、「折り紙つき」を、「偉い人の保証がある」場合は「お墨付き」を使うようにしましょう。
まとめ
「折り紙つき」と「お墨付き」の違いについて見てきました。
2つの言葉には明確な意味の違いがありました。
2つの言葉の意味の違いを知ることで、混同せずに使い分けることができるようになりそうです。