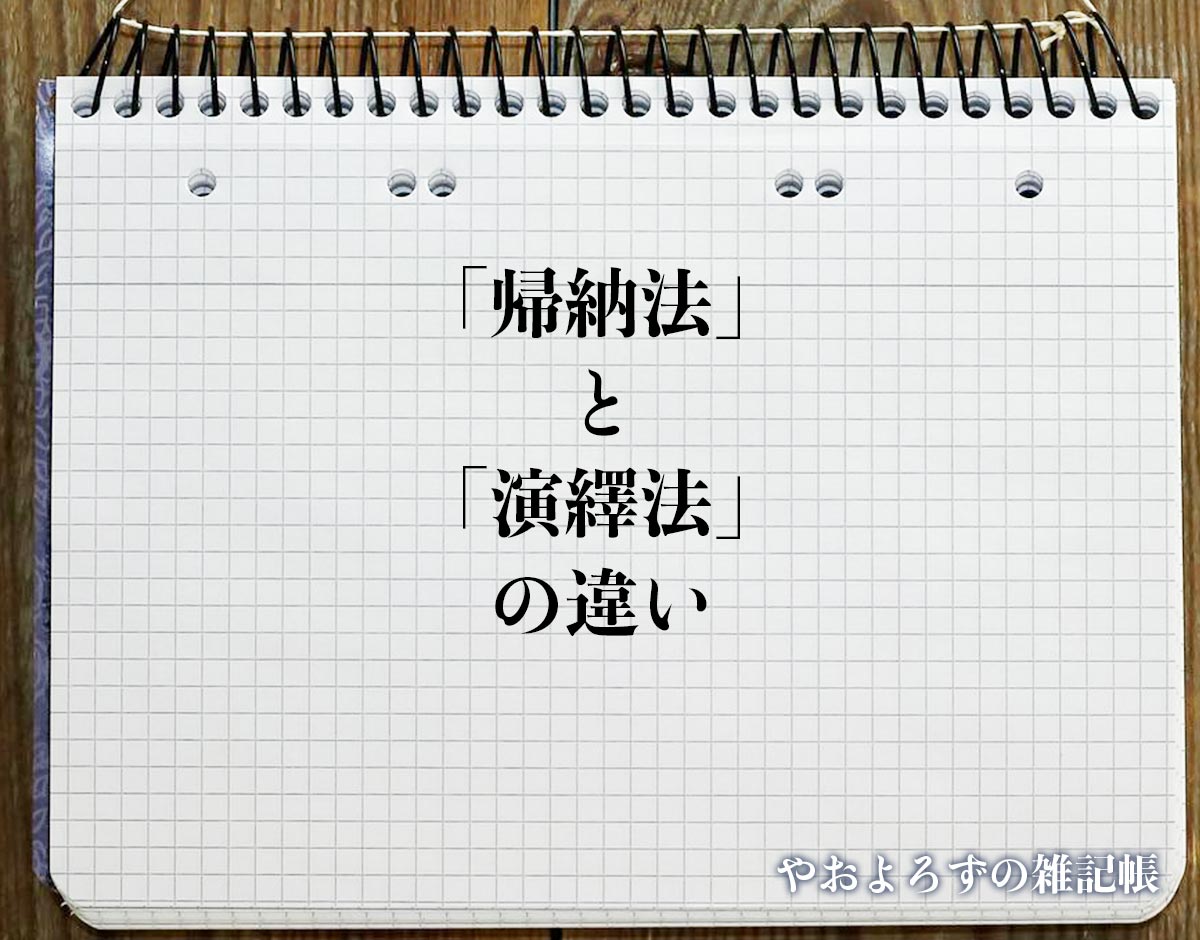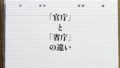この記事では、「帰納法」と「演繹法」の違いを分かりやすく説明していきます。
「帰納法(きのうほう)」とは?
「帰納法」とは、「いくつかの事例や事実から見られる共通点をまとめ、その共通点から分析される根拠を基に結論を導き出す方法」を意味する言葉です。
「帰納法」はイギリスの哲学者である「ベーコン」によって意味付けられ、同じくイギリスの経済学者であり思想家である「ミル」によって大成されました。
「帰納」は「個々の観察された事例から、一般に通ずるような原理や法則を導き出すこと」などの意味を含める言葉です。
「演繹法(えんえきほう)」とは?
「演繹法」とは、「三段論法に代表される、演繹による推理の方法」を意味する言葉です。
「三段論法」とは、「2つの前提から1つの結論を導き出す論理的推論」を意味します。
例としては、すべての人間は死ぬ(前提1)→ソクラテスは人間である(前提2)→したがって、ソクラテスは死ぬ(結論)のような推論です。
「演繹」には以下の意味が含まれています。
・「1つの事柄から他の事柄へ押し広めて述べること」
・「与えられた命題から、論理的形式に従って推論を重ね、結論を導き出すこと」や「一般的な理論によって、特殊なものを推論して説明すること」
「帰納法」と「演繹法」の違い
「帰納法」は複数の事例や事実から見られる共通点から分析できる根拠を基に結論を導き出す方法のことです。
一方、「演繹法」は演繹による推理の方法のことです。
それぞれの推論の違いを「人の死」を例に見ていきましょう。
・「帰納法」
Aはいずれ死ぬ→Bもいずれ死ぬ→Cもいずれ死ぬ→したがって、人はいずれ死ぬ(結論)。
・「演繹法」
全ての人はいずれ死ぬ→Aは人である→したがって、Aはいずれ死ぬ(結論)。
まとめ
・「帰納法」とは、「いくつかの事例や事実から見られる共通点をまとめ、その共通点から分析される根拠を基に結論を導き出す方法」を意味する言葉です。
・「演繹法」とは、「三段論法に代表される、演繹による推理の方法」を意味する言葉です。